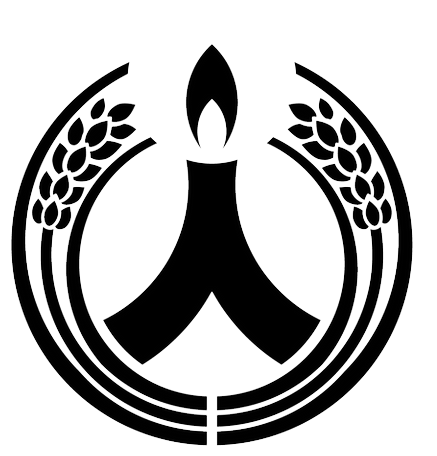令和7年の新年度が始まる!

東京靖国神社の桜開花宣言に続いて全国から桜の満開宣言がなされています。
「サクラ」は我が国の国花であり、「日本人のこころ」、「日本精神」と結び付けられて日本人に愛されてきました。3月末から4月上旬という非常に短い期間に咲いて、一気に散ることからその儚さが日本人の美学の象徴となっています。年度末から年度始めに掛けて卒業、入学、入社という人生の一大イベントの時期がこの時期にあり、桜はそれを盛り上げる役割を果たしています。
日本人と桜の歴史は、古く平安時代に遡ります。『日本後記』という歴史書に、嵯峨天皇(第52代:786-842)が枝垂桜の鑑賞をしたという記載があり、その頃が日本人の花見のルーツと言われています。爾来、時代を超えて桜は日本人の心に脈々と受け継がれました。後醍醐天皇がお住まいだった奈良の吉野の千本桜は、後醍醐天皇の国に対する思いを今日に伝える貴重な風景です。日本人として生涯に一度は訪れたい日本人の心の原風景だと思います。
今年は、昭和維新100年、大東亜戦争終結80年の節目の年にあたり、崩れ往く日本人、日本のこころをしっかりと繋ぎ止め、次世代に残す為にも、子供たちと花見をして、桜と日本人の絆を再認識したいものです。我が街、姫路城の桜は、4月6日に開花宣言の予定となっています。
3月24日~3月31日の間に開催された定例講座は以下の通りです。
▼3月26日 水厚会講座『宋名臣言行録に学ぶ』(田中昭夫先生)
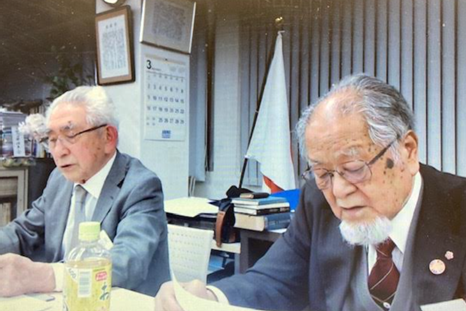
今回は、前回の第二章「政治の要訣は人事にあり」の続きから始まりました。「反みて徳を修める」の最初は、呂公著の「人心或はいまだ服せざることあるときは、則ち反て徳を修め、温怒を以てこれに加えず」という言葉から始まりました。部下と相対する時にはどのように接すれば良いかということです。名宰相と呼ばれた人たちは、古人の言葉を身に刻んで日常の業務に当り、その結果、後世に名を残すような人物になっていったことが伺えます。
▼3月27日 岡田武彦先生の著作に学ぶ『簡素の精神』(三木英一先生)
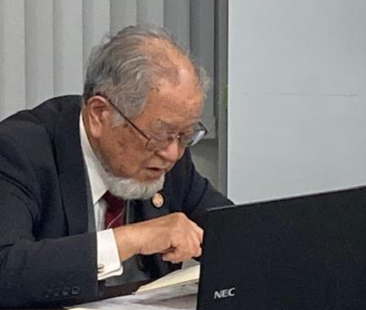
今回は『簡素の精神』の第二章「簡素の形態とその精神」を味読しました。最初の「自然の性情」では、文人画の発達を文人画家の作風をベースに論ぜられています。それは、次の章の「以心伝心」において、禅文化と結びついて日本に流入し、日本の鎌倉、京都の五山文化の形成に大きな影響を及ぼすことになりました。岡田先生の終生の研究対象であった王陽明は、「易学」と「禅」の思想を中心にして思索を凝らし、陽明学として開花させたのです。