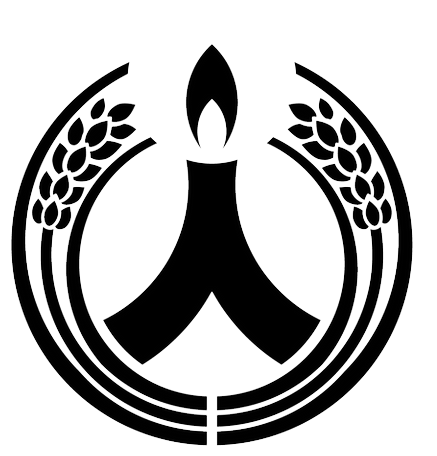乙巳の年、上半期が終わり、下半期に何を期待するか。

梅雨なのに雨の少なかった今年の梅雨、お米の生育と水不足を心配するのは私だけでしょうか?今年の上半期を振り返って、先ず、大きな事件といえば、「令和の米騒動」でしょう。この騒動は昨年の夏頃から始まりました。我が国の主食であるはずの米が今までのように買えなくなり、価格が高騰し、とうとう政府備蓄米の放出という事態になりました。平成の時代にも米騒動がありましたが今回とは次元が違うようです。平成の米騒動は平成5~6年に起った時は、夏の大冷害で米の作況指数は74となり「著しい不良」と発表されたことに端を発しました。今回の令和の米騒動は、非常に深刻です。原因は政府の減反政策、気候変動による不作、需要の増加とそれに対する政府の対応の遅れ、判断ミスが重なるという複合化要因と言われますが、高度化した文明社会において人間が人間として判断し、意志決定しなければならないことを怠った結果です。これは政治、行政の大失敗といっていいでしょう。それに対し誰も責任を問われない、今後の改善に対する議論もされていません。政治がここまで混乱し停滞していることでしょう。
世界に目を向けると、トランプ政権の立ち上がえりと同時に「トランプ関税」の嵐が世界に吹きまくり、米中の対立が如実化し、中東では第三次世界大戦勃発の危機に至っています。「今だけ、金だけ、自分だけ」の無勝手主義が世界の秩序をズタズタにしています。この事態を糾すことの出来るのは、日本と欧州諸国しかありませんが世界的に見ても事を収拾出来る大人物がいないという嘆かわしい状態です。そんな中で日本の武士道精神を現代社会で実現して見せているのが米メジャーリーグで活躍する大谷選手です。彼の示す動作一つひとつが人々に感動を与えています。世界は日本の「大岡裁き」を待望しています。
7月20日には参議院議員選挙が実施されます。今年の下半期の始まりは此れからの日本の明暗を握る大事な選挙になりそうです。今こそ、日本は「令和の維新」に向けて動き出さねばならないのです。
6月24日~6月29日の間に開催された定例講座は以下の通りです。
▼6月25日 姫路水厚会講座『宋名臣言行録に学ぶ』(田中昭夫先生)
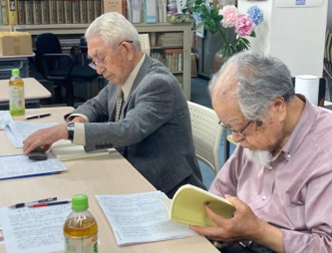
第九回の今回は宋代に行われた大改革「王安石の新法」の実践とその成否を学び、その後、登場した司馬光の政治についてまず学びました。王安石の新法の推進派の王安石とその反対派の司馬光が如何に論戦を繰り返し、結局、新法は崩れ、最後は互いにどうなったのかという人間模様は我が国江戸時代の三大財政改革と併せて読むことで、我々は大いなる教訓を得られます。
▼6月26日 岡田武彦先生の著作を読む(三木英一先生)
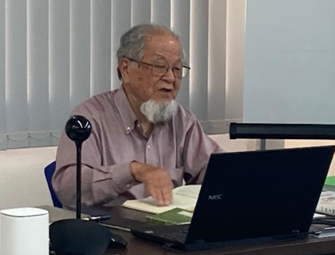
『簡素の精神』の第十回は「俳句」にみる簡素の精神でした。世界で最も短い詩的表現である俳句の誕生と、その集大成者である松尾芭蕉の生涯と作句紀行を廻りながら、芭蕉の俳句を楽しみました。