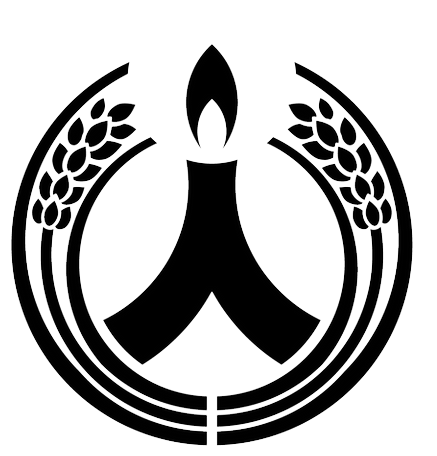400年前の先人に学ぶ世直しの極意 (平成七年熊澤蕃山先生を偲ぶ会)

先師安岡正篤先生が当代随一の経世家と評する「熊澤蕃山」先生の歿後334年目の遺徳を偲ぶ会が岡山県備前市の日光山千手院正楽寺で開催されました。
今年は朗読と講演の二本立てのプログラムで、第一部は地元蕃山出身のフリーアナウンサー志村永子氏による朗読「風の武士 熊澤蕃山」でした。蕃山先生は39歳で岡山藩を辞し、当時寺口村と呼ばれた現蕃山村に隠棲しました。そこで経世家としての手腕が発揮されます。その模様を熊澤蕃山先生顕彰会会長の立花が書き下ろされた「風の武士 熊澤蕃山」で読み聞かされました。
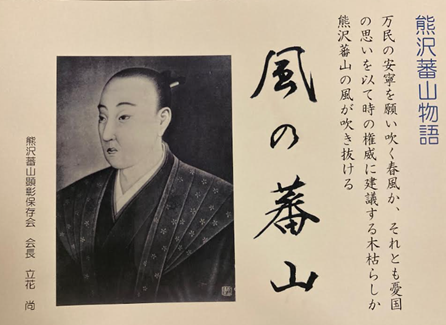
江戸時代初期の元和五年(1619)に京都の稲荷(今の伏見区深草付近)に生を受け、八歳の時に母方の外祖父熊澤守久の養子となり、武士としての教育をみっちり叩き込まれたことが彼を天才経世家に仕立て上げるベースになりました。時の名君岡山藩藩主池田光政侯の元で藩政というものを学びながら、その非凡な才能を開花させていったのです。戦のない平和な社会で蕃山先生が直面したのは困窮する武士、庶民の暮らしです。幼少時より四書を学び、「経世済民」こそ武士の使命であると教えられて生きてきた蕃山先生は、世直しの必要性を感じ始めました。蕃山村での生活の後、経世家としての手腕を買われ、豊後岡藩の民政指導に当たり、その後、京都に移り住み私塾を開き、学問思想を形成していきました。蕃山の名声が京都で高まるほどに幕府は蕃山の思想、影響力を懼れるようになり、49歳の時に京都から追放され、明石松平信之の許にお預けとなりした。その時に、時の将軍徳川綱吉に宛てて下ろされたのが、『大学或問』という問答形式の書物です。

これは、二十一章からなる世直しに関する問答です。第二部では、蕃山研究家の山谷和子氏による講話『大学或問』でした。自身が編集し、書き下ろされた『大学或問』の冊子とスクリーンに投影された写真、図を交えて一時間余りの講義をされました。自作の漫画を元に難解な『大学或問』を分かり易く解説されたとてもいい講話でした。
どの地域にも偉人先哲が存在します。今の日本にとって大事な教育は「郷学」です。先人が如何に学び、如何にして人物を練り、如何にして形声済民したのかを学ぶことが今を生きる私たちにとってはとても大事なことです。当塾のみならず、師友道友は須らくこの精神で「郷学振興」に尽力せねばなりません。
8月25日~8月31日の間に開催された定例講座は以下の通りです。
▼8月28日 岡田武彦先生の著作に学ぶ『簡素の精神』(三木英一先生)
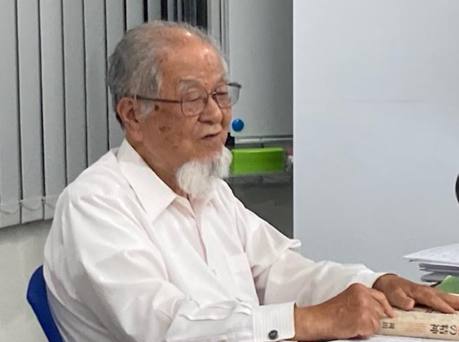
今回の講義は、「日本絵画」に見られる簡素の精神から始まりました。
日本人は没個性的、創造性に欠けるといわれます。絵画の世界においても大陸からそれが流入するや否やそれを受容して大きく開花させ、後には逆に情感を込めて表現し、輸出するようになるのです。水墨画、文人画と大きく発展し、の雪舟は大陸に渡り、最新技法を学び、帰国して大陸から教えを乞いにくるくらいになっています。江戸時代の俵屋宗達、尾形光琳の技法は日本絵画が世界に羽ばたかせ、東洲斎写楽や喜多川歌麿の浮世絵は世界で大絶賛されています。
絵画のみならず、書道、建築の分野においても我が国は外来文化を受容し、二部で消化し、情知を加えて簡素化してきたことを学びました。