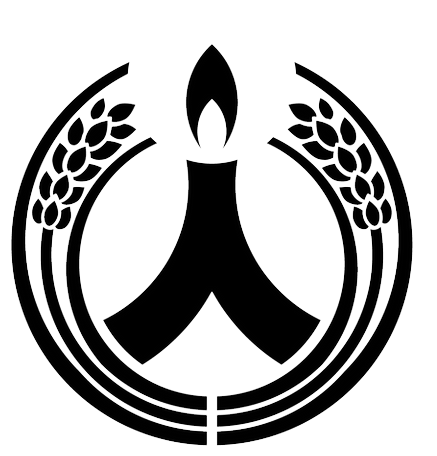第二回 自然忌(岡田武彦先生の遺徳を偲ぶ会)開催迫る!

郷土の先人 岡田武彦先生の歿後21年目に当たる来月10月17日に当たり、第二回の自然忌を開催し先生のご遺徳を顕彰いたします。今年は当塾の理事長竹中栄二による岡田先生の著書『王陽明紀行』を読むという内容で先生の業績を紹介いたします。
昨年の第一回自然忌を機に、三木英一先生の「『簡素の精神』を読む」の講義を一年間続けてまいりました。世界的な王陽明研究者である岡田先生が日本人への遺言の様に書き残された『簡素の精神』を読み進めるうちに、外国の文化を学べば学ぶほど、日本及び日本精神、文化の崇高さ、素晴らしさを実感します。やはり、我々は民族の歴史を大事に宝物として伝え続けて行かねばならいことを実感しています。こ
今年の自然忌は岡田武彦先生のライフワークでもあった王陽明の事績巡りが集大成された『王陽明紀行』を読み解きたいと思います。
9月22日~9月28日の間に開催された定例講座は以下の通りです。
▼9月25日 岡田武彦先生の著作に学ぶ 第13回(三木英一先生)

『簡素の精神』の味読も11回目となりました。今回は第三章の「日本文化にみる簡素の精神」でした。前回の復習もかねてまず「伊勢神宮」に見られる「簡素の精神」です。日本神道は自然との一体を旨とします。伊勢の森の中に見られるお社は樹齢300年を超えるご神木、木曾ヒノキにより形造られています。アインシュタインもトインビーも絶賛した日本の簡素美の究極です。
次いで、桂離宮、天龍寺にみる日本庭園の簡素美を学び。その後は日本の陶器、茶木にみる簡素性について学び、その究極の形として裏千家の「茶の湯」における簡素性を学びました。
▼9月28日 「伊與田人間学を学ぶ」第七期『続 有源山話』第8講
(竹中栄二先生)

今回は第4章 「論語と日本」神在すがごとくの二回目でした。今回も平安時代に編纂された『六国史』の続き、『続日本後記』の仁明天皇の記述にみる論語の章句を学びました。第53代の淳和天皇、第54代仁明天皇、第55代の文徳天皇の事績にみる『論語』の章句、「神を祭ること 神在すが如く」「徳は弧ならず 必ず鄰り有り」、「文徳を修めて以てこれを来たす」等の文句が『続日本後記』や『日本文徳天皇実録』の中に見られることから、285年、応神天皇の御代に渡来した『論語』の教えが、天皇家で600年間読み継がれて、国政の基になっていることが伺い知れました。